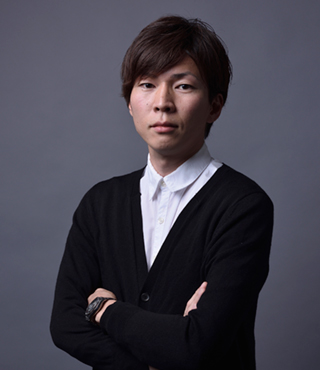GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE 2024GPHG 2024特別番外編 2024「GPHG」受賞 - 2025「9号」発表 02
2024年11月13日(水)、ジュネーブGPHGに登壇!

2024年ジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプ(GPHG)の「チャレンジウォッチ賞」受賞作品、大塚ローテック「6号(No.6)」。上部(分針)、下部(時針)のダブルレトログラード式表示機構搭載。中心部は秒ディスク、その右に日付表示。2015年の発表後2023年に新仕様へと変更。モデル番号と時刻表示の洋数字以外はすべて和文で表記されている点に、あらためて日本時計の誇りを感じる。「豊島」まで表記するこだわりが片山次朗氏の個性。
2024年11月11日(月)の週は、大塚ローテックの片山次朗氏にとって記憶に残る1週間となった。まず、3カ月前の8月28日に「6号」が「ジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリ(GPHG:Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 」のチャレンジウォッチ賞(3000スイスフラン以下の時計)にノミネートされ、さらに片山氏には文部科学省の令和6年度「現代の名工」に選出されるという名誉も加わる。また香港ではマーク・チョー氏と会い能登半島チャリティ・イベントへの出席も控えていた。
この週、片山氏は11月11日(月)に東京・リーガロイヤルホテルにて「現代の名工」表彰式に出席し、その夜へスイスへ飛び11月13日(水)のGPHG2024授賞式に出席、さらに香港へ飛び帰国するという往復約2万4000kmのハードスケジュールを1週間で強行した。まるで夢のような7日間だったと思われるが、ジュネーブへ飛び立つ直前までGPHGの受賞の行方は分かっていなかった。本当に受賞するか否かは分からなかったのである。2023年にGPHGの最終審査員を務めた飛田直哉氏(NH WATCH株式会社 代表取締役)に以前尋ねたところ、「全受賞者は授賞式当日に決定されます。最終審査委員は授賞式当日、朝の8時から授賞式直前の夜の7時まで、途中ティーブレイクも入れながら延々と約11時間激論し、その結果受賞者を決めるのです」とのことだった。しかし、たとえ受賞しなくても、この日はスイスやフランス、ドイツその他の国々から錚々たる時計関係者が集結する。彼らとの情報や名刺交換だけでも行く価値は十分ある。
エントリーから受賞までの経緯を片山氏は以下のように述べる。実際、他者からの推薦は多かったようだ。
「2024年の6月頃、GPHG協会からメイルが届きました。そのエントリーページを開いたら『このような方達からの推薦を受けていますが、どうされますか?』と書かれています。“小さな針”賞とチャレンジウォッチ賞等の枠に推薦されていたので、チャレンジウォッチ賞にエントリーしました。6月の半ばにはエントリーは済ませました。
順番としてはエントリー→ノミネート→グランプリとなるのですが、9月の中旬か末頃にノミネートに残ったことが判明しました。しかし受賞するか否かは、11月13日(水)の発表・授賞式の本番まで分かりません」(片山次朗氏。以下同)
GPHG本部から次の連絡が届いたのは、11月の本番直前だった。「主催者側から『あなたたちはノミネートされたので一般客の席を用意しました。ですので、もしスイスまで来られるのなら来て下さい』というメイルが届きました。元々、GPHGを見に行く計画はあったので、旅行の日程は組んであったのです。ラス・ミュージアム(GPHGの全ノミネートモデルを展示。P.03参照)の見学や『5号改』をラ・ショー・ド・フォン国際時計博物館(MIH:Musée International d'Horlogerie )へ寄贈する計画もありましたので」
ちなみに大塚ローテックが2023年に発表した「7.5号」のシリアルナンバー0番は、すでに同年5月にこの国際時計博物館に収蔵されている。
さて本番。GPHGの発表・受賞式は、恒例となったフェアモント・グランド・ホテル・ジュネーブの地下にある“テアトル・デュ・レマン” (Théâtre du Léman)である。このような経緯で11月13日にの授賞式に挑んだ片山氏だが、最終審査員とは違いノミネートされた時計会社への旅費や宿泊費は用意されない。しかし一般客用の席は用意されていた。

壇上に勢揃いした受賞者たち。前列一番右端に並ぶH.モーザーCEOのエドゥアルド・メイラン氏やショパール共同社長のカール-フリードリッヒ・ショイフレ氏は常連。片山氏は最後列左端に控えめに見える。彼の斜め前(向かって右)にはローラン・フェリエ氏、その後ろにはMINGのMing Thein氏の姿も見える。
※GPHG2024のHP:https://www.gphg.org/en/gphg-2024
思いの外、緊張したセレモニー
ジュネーブでのGPHG授賞式の印象を尋ねたところ、
「予想以上に緊張しましたね。すべて真っ赤な世界で……(註:劇場のシートやステージでのカーペットやカーテンは赤を基調としている)。時計版のアカデミー賞やグラミー賞っていう感じでしょうか。私の席の周りにはこれまで本(や雑誌)で見た人たちが居るわけです。マーク・ニューソンの後頭部が見えたりして、これはヤバいなという感じです。
そうしたら、席に座ったタイミングでどんな賞を頂けるのか、順番はいつかということを協会の人からいきなり聞かされました。『あなたは最初です』と。それまで受賞できるのかさえ、聞かされていなかったのですが、とにかく最初にスピーチをするのはあなたです、と言われました。つまりその言わんとするところは……、ということなんでしょうね。
壇上に立つまでは(具体的な内容は)一切聞かされなかったです。とにかくコンフィデンシャルに会を進めていました」
2023年に最終審査員を務めた飛田氏は、自身が投票した時計に関しては他言無用の誓約書にサインした。審査員に対してもノミネートされた側にも、一切が秘密主義の元に行われているのは確かなようだ。
いよいよ片山氏はライト煌めくステージへ登壇しスピーチを行ったが、本人はよく覚えていないと言う。
「英語で2分ぐらいかな、一応(受賞の時のために)3日前ぐらいに考えていたのです。それを添削してもらって、空で言えるように暗記して、でも結局できなくてスマホを持ってそれを見ながら喋りました」
スピーチ後、壇上にスマホを置き忘れるというハプニングもあったが、本人は感無量だったようだ。
「嬉しかったですね。僕は元々プロダクトデザイナーで、時計の世界出身じゃなかったものですから。たまたま工作の勉強をして、時計を題材にして作り始めたらこうなったのです。当時は情報もなかったので、GoogleやYoutubeで色々な人の作品を見て真似をしていました。それが(GPHGという)世界に立つことができて、夢のようなことです。これまで動画で見てきた時計師達が、会場のそこらへんにいるので舞い上がりました。
プロダクトデザイナーとして、多少はプレゼンテーションの場数を踏んでいたので慣れてはいましたが、会場はフランス語だし僕のスピーチは英語だし、左右見たら見たことのあるような人たちがいますし、何行かスピーチは飛ばすし、まるで地に足が着いていないような感覚でした」
立ち見客まで出て、およそ1000人以上の時計関係者の前でのスピーチは、想像するに余りあるほどの緊張感だったに違いない。しかし、日本の東京・大塚に工房を構えるひとりの日本人が、スイス、フランス、ドイツ等欧米時計人の前で堂々と立つ姿は、日本のメディアとして、また同じ日本人として実に気持ち良い。日本時計の底力と個性は世界で通用することを、片山氏は見事証明した。
-

片山次朗
Jiro Katayama
1971年、東京生まれ。1993年、東京コミュニケーションアート専門学校卒業。その後、トヨタグループに属する自動車メーカー、関東自動車工業株式会社でカローラ、アルテッツァ、ファンカーゴなどのデザイン開発を担当。1998年に独立し、フリーランスのプロダクトデザイナーとしてカメラ・レンズやヘルメットのデザインを手掛ける。2008年、デザインを手がけたタムロンのカメラレンズがグッドデザイン賞受賞。同年、ネットオークションで入手した卓上旋盤を用いて、Youtubeを参考に時計ケースの製造を始める。以降、本格的な時計製造へと発展し2012年に「5号」発売を契機に大塚ローテックを創業。2024年、厚生労働省が定める「卓越した技能者(現代の名工)」に選出。同年11月「ジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリ(GPHG)2024」のチャレンジウォッチ部門で受賞。
取材協力:片山次朗(大塚ローテック)
Special thanks to:Jiro Katayama(ŌTSUKA LŌTEC)
©FONDATION DU GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE
INFORMATION

大塚ローテック(OTSUKA LOTEC)についてのお問合せは・・・
大塚ローテック
大塚ローテック ブランドページを見る