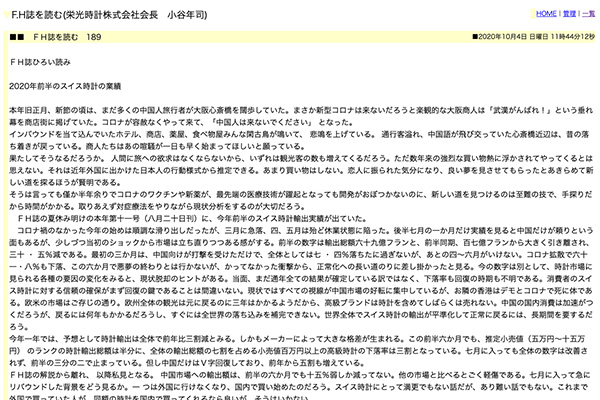栄光時計「時計店を軸としたカルチャー・ソサエティ作り。それが、これからの小売店のあり方です」 01
戦後の混乱を乗り越え
時計卸で創業した栄光時計

「ラグジュアリー産業の基本はフランスであり、ワイン。これがフランスのマーケティングを決定しています。どこの畑か、何年からやっているか、どんな城館を持っているのか、数もむやみに増やさない。逆に日本人は数を増やしたがる。そして、日本のエンジニアは安くて良いものを作ったら売れると思っていて、作る技術は持っているけど神話の作り方は下手ですね」
『サントノーレ』、『シャリオール』、『モバード』、『クロノスイス』など、通好みのウォッチ・ブランドから華麗で豪奢なジュエリーに至るまで、欧米の有名時計宝飾品の輸入代理店として知られる栄光時計。現在では2016年に分社化しホールディング制に移行しているが、その母体となったのは小谷稔氏が終戦直後に創業した栄光時計である。
小谷稔氏は戦前、服部時計店(現在のセイコーホールディングス)に勤務し中国市場などを舞台に活躍したが、戦後に退職し、時計卸業を行う栄光時計を創業した。
その小谷稔氏のご子息であり、二代目である小谷年司さんは、まさに戦後輸入時計の生き字引的存在。実際の体験に基づく数々のエピソードがめっぽう面白い。そこで栄光時計が本社を置く大阪博労町を訪ね小谷会長にお話を伺うことにした。
そもそも栄光時計という会社は、どのようにして設立されたのでしょう?
「戦前に服部時計店の大阪支店があったんですが、そこが一種の独立国のようで、相当の力があったんです。私の父は、その大阪の服部時計店に丁稚で入ったんですね。当時、大阪の服部時計店は中国北部から満州の商圏を支配し、東京の服部時計店は上海をはじめとする中国南部の商圏を抱えていたんです。そこで私の父は中国北部商圏の支配人だったそうです。
また、服部時計店は大阪支店内に『服部商業学校』というのを作って中等教育を行い、時計関係者の師弟を養育していたんです。
それで戦後、父が服部時計店を退職して創業したのが『栄光時計』です。“栄光”という名称は、父の相棒がクリスチャンだったからで、“神の栄光”という意味が込められています。創業にあたっては、当時の服部時計店三代目社長の服部正次さんから、『セイコーを売って良い』と言われたと聞いています」
国産時計の卸からスタートし
高度経済成長期にスイス時計を扱い開始
こうしてセイコーの卸問屋としてスタートした栄光時計だが、やがて他社の時計も扱い始めた。
「実はセイコーの時計だけでは、なかなか経営が厳しくて、それで国産ではタカノ(1962年にリコーに買収された)やオリエント、さらにスイス時計も扱い始めたわけです。当時、スイス時計はオメガが主力で、これはシイベルへグナー(現・DKSHジャパン)が扱っていましたね。
それと前後してIWC(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー)やオーデマ ピゲも扱い始めました。
ただし、我々のような問屋はマーケティングはせず、主にシイベルへグナーやリーベルマンなどの輸入代理店がマーケティングを担当していました。また、パテック フィリップは香港にいるスイス人がその権利を持っていて、その後、一新時計が間に入って輸入が始まりました。さらに酒田時計貿易がラドーを、平和堂貿易がピアジェなどを扱うようになって、戦後のスイス時計ブームが興ったんです。
中でもラドーは強かったですね。しかし問題は上から10のブランドを数えたら、あとは、その他大勢だったことです。結局、日本で人気があったのはスイスの大手だけでした」
ラグジュアリー・ブランドのマーケティング
その原点はフランス・ワインにあり
長年、問屋や輸入代理店としてスイス時計をいわば内側から見てきた小谷会長だが、もっとも記憶に残っている出来事はなんでしょうか?
「私がこれまでの時計人生で一番、不思議に思ったのは、2000年にボーダフォンがマンネスマン・グループの通信部門を買収したことが発端となって、リシュモングループがA.ランゲ&ゾーネやジャガー・ルクルト、IWCなど、合わせて年商数百億円の時計会社を、その約10倍もの価格で買ったことです。私は、数千億円も出せるなら自分で工場作った方が良いと思ったんですが、ブランドというのは単にお金を出してもできないんですよね。
たとえば、ある宝石会社は年間200億円もの予算で宣伝を続け、ブランドの浸透を図りましたが、思ったほどの利益を上げていない。映画も同じ。お金を出したからといって良い映画ができるわけじゃない。でも、お金を出さないと良い映画はできない。難しいものです」
そんな小谷会長にとって思い出深いブランドが、1980年代から輸入を手掛ける『シャリオール』だという。
「栄光時計が本格的にスイス時計の輸入を始めたのは『シャリオール』からです。これは、ある日、突然社長のフィリップ・シャリオールさんがやってきて『小谷さん、一緒にやろう!』といったことがきっかけです。
シャリオールさんは、カルティエでニューヨークや香港の支店代表を務めていましたから、ブランドの作り方、売り方を知っていた。私は彼の話を聞き『スイス人やフランス人は違うなあ』と思いましたね。やはりラグジュアリー産業の基本はフランスです。その原点はワイン。ワインというのはフランスのマーケティングを象徴しています。美味しいとか、美味しくないだけではなく、どこの畑か、何年からやっているのか、どんな城館を持っているのかが大事。しかもボルドーでは新参者は受け入れず、加盟は60社だけ。生産数もむやみに増やさないと決めている。
日本人は売れるとなると数を増やしたがりますが、それでは駄目なのが、ラグジュアリー・ブランドのマーケティングなんですよ」
モノの作り方は知っていても
売り方を知らない日本人
「だからシャリオールさんも取引先の数を減らせといった。『あなたはどこでも売りすぎる。でも、販売の窓口を減らすことで売り上げが上がる』というんです。
ただ、私はこんなに長く、高級時計のブームが続くとは思っていなかったね。私の若いころは8000円ぐらいの時計が普通で、一昔前でも5万円とか8万円すれば、それが高級時計だった。それが今や50万円が普通になったでしょ」と小谷会長は驚きを隠さない。
「私はブランドについて懐疑的でね。つまりブランドというのは非常にヴァーチャル。ないものをあるかのように見せるという。その技術が今やマーケティングです。それを非難するわけではないけど、今の世の中すべてマーケティング。観光も宗教も。ただ、フランス語を勉強したことで救われました。スイスの時計界は基本フランス語ですから、彼らと直に渡り合えた。
日本のエンジニアは安くて良いものを作ったら売れると思っていますが、決してそうじゃない。たとえば茶道具。高いものほど良く売れる。ものの価値や価格はバーチャルなんです。
時計も似ています。今は時計が趣味の世界に近づきつつあるから、大量生産で良いものを安くというなら、ロシアなど他の世界に行く必要がある。
大体、“虚栄の価値”というものを日本のメーカーは知らないんです。神話の作り方が下手。作る技術は持っているけどね。つまり、お客さんは夢を買っているんですよ」
時計小売店と時計見本市の
未来展望とは?
2020年は新型コロナの影響で大型の時計見本市が開催されず、しかもバーゼルワールドから多くのブランドが撤退を表明するなど、大変革期を迎えているスイス時計界。これからスイス時計界はどうなるのか、あるいは、どうなるべきとお考えでしょうか?
「最近のバーゼルが大きなブランドが主力で、あきらかに来場者が減っているところを見ると、19世紀後半に印象派の歴史が独立した画家が開いた展覧会から始まった時のように、時計見本市も、いずれ小さなメーカーやブランドが集まって開かれるようになるのじゃないでしょうか。
時計の小売も主体がブランドのブティックになっています。そうなるとデパートなどで、そのブランドを扱わないのが必然ですが、今はまだ扱いが続いています。ただ私は、扱えないブランドがあるならあるで、それなりに楽しい店作りができればと思っています。
それにフリート(艦隊)主義というのか、あるブランドを扱うなら全製品まとめて扱うのが基本になっていますが、私は店主の趣味でブランドも製品も絞り込んだ店ができないかなと願っています。
最近では都会での生活が嫌になり、田舎でカフェを開いたりワインを作ったりする人がいますが、時計もそうならないかなと思うんですよ。
たとえばツタヤのように、立ち読みも許し珈琲まで出すとか。しかもそれでよく売れるんですからね。そういう発想を時計店も、カフェやバーとタイアップしたりして、ある種のカルチャー・ソサエティを作ればいい。どの店も、“置いたら、すぐ売れる”というものばかり見つけて並べようとしています。まぁ、それが成功の鍵ではありますが、それだけでは、どうしようもないんですよ。
小売店も良いものを見る目はあっても ブランドの言いなりになっているような気がします。また、小売店のネット販売は今の所、低調ですがやり方次第。ヒューマンタッチのある売り方とネットが両立しないはずはない。これを実現させないとなりません」
小谷会長の話はまだまだ尽きないが、機会をいただければ、さらに深いお話を伺えればと思っている。
取材・文:名畑政治 / Report&Text:Masaharu Nabata
撮影:嶋田敦之 / Photo:Atsuyuki Shimada